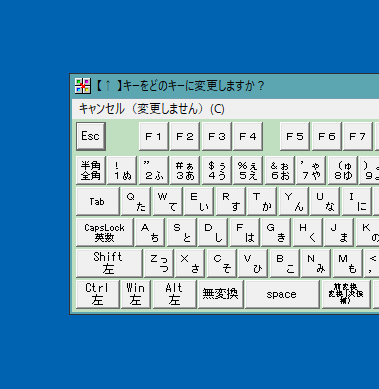認識の解像度・速度とクオリアの関係について考えていること
クオリアという言葉について、僕自身が正確に理解しているか怪しいけど、この投稿ではとりあえず、「五感への刺激が引き起こす、その人の内側だけで感じられる質感で、感情もこれに含む。」としておこうと思う。 僕が考えていることは、「刺激を学習して、それに対する解像度が上がって処理速度が上がると、クオリアを感じにくくなるのはなぜか。」ということ。 まず、僕の主観と経験をもとに、クオリアを感じにくくなった例を挙げてみる。 音楽によって起こるクオリアは、個々の楽器を別々の音として認識できない(意識しない)時の方が、その音楽特有のクオリアを感じることができる。曲の中にどんな楽器が使われているのか、ほとんど知らなかった小学生の頃は、基本的にボーカルとそれ以外といった感じで聴こえていたように記憶している。曲の中からメインメロディを抽出することはできても、ベースやドラムの音は特に他の色々な楽器たちと一体で聴こえていて、分離して認識することはできなかった。そのためか、小中学生の時に聴いていた曲を久々に聴いてみると、クオリアを強く感じられる。 なぜ分離して認識できなかった楽器を覚えているのかというと、中学になって曲の耳コピをし始めた時、「この音色はこういう楽器の名前で、こういうフレーズを弾くんだ。」というのを知り始めて、途端に色々な楽器を別々に聴き取れるようになったのを覚えているから。 続いて高3の秋ごろ、楽典の勉強をしていた頃の話。気付いたら、曲中のほぼ全ての楽器の弾いている旋律の相対音程をリアルタイムにキャッチしたり、4和音以上のコードのクオリティも即座に判別できるようになってしまった。音楽に対する解像度はこれを機に爆上がりしてしまい、これ以降長い間、音楽を無心で楽しむことができなくなってしまった。しかし、眠りに落ちる直前のギリギリ外界の音が聞こえている状態の時だけは、脳みそが分析をしないでいてくれるのか、昔のように音楽を一つのまとまりのある質感を持ったものとして感じられることがあった。ウトウトしてる時に出会った曲に対しては特別な感情が湧きやすく、目が覚めてから必死で探すことが多い。しかし、目が覚めている時にその曲を聴きすぎると、だんだん何も感じられなくなってくる。今でこそ分析的に聴いてしまう癖がだいぶ抜けて、無心で聴けるように戻ってきたが高3から大2の間にヘビロテして聴いてしま...